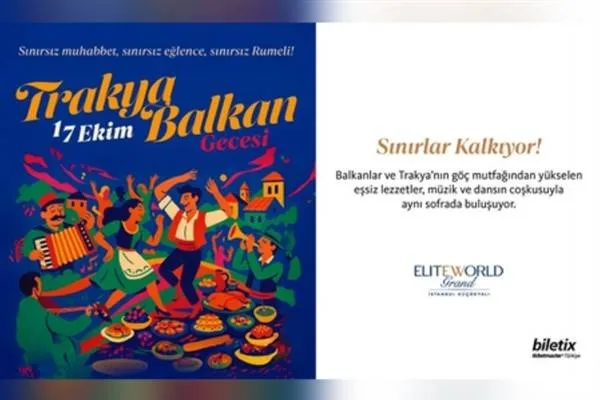調査:産油国を含む最も裕福な国々も気候資金を受け取っている
イスタンブール、11月15日(Hibya)-世界最大級の経済である中国に加え、サウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)などの裕福な産油国も、気候資金として多額の資金を受け取っている国々の中に含まれている。
気候変動の科学と政策を専門とする英国拠点の組織カーボン・ブリーフ(Carbon Brief)と英紙「ガーディアン」は、これまで報告されてこなかった国連(UN)への提出文書や経済協力開発機構(OECD)のデータを分析し、地球温暖化対策のために拠出された数十億ドル規模の公的資金がどのように使われているのかを明らかにした。
ブラジルで開催中の国連気候変動会議2025(COP30)に合わせて発表された本調査は、富裕な大規模排出国から脆弱な国々へ資本が移転され、それらの国が自国の経済をクリーン化し、より温暖な世界に適応することを支援する、概ね機能している仕組みが存在することを示している。
しかし同時に、これらの資金の大部分の配分は中央での監視の対象となっておらず、各国の裁量に完全に委ねられているため、政治的な利害の影響を受けやすく、資金が必ずしも最も必要とされる場所に届いていない実態も浮き彫りになった。
公式データはすべての気候資金受益者を追跡するには十分網羅的ではないものの、「ガーディアン」の分析によれば、2021年と2022年の資金のおよそ5分の1が、世界で最も貧しい44カ国、いわゆる「後発開発途上国」に流れていた。しかも、その多くは助成金ではなく融資の形で提供されていた。
これら後発開発途上国の中には、受け取った気候資金の3分の2以上が融資であり、その返済条件によって政府がさらに深刻な債務のわなに陥るおそれがある国もある。バングラデシュとアンゴラでは、融資の割合が95%、あるいはそれ以上に達していた。
世界の多くの先進国は、開発途上国での気候行動を支援するため、二国間援助や開発銀行などの多国間機関を通じて資金を供給している。2009年にコペンハーゲンで開かれた国連サミットでは、富裕国は気候悪化に対する自らのより大きな責任と、解決策を資金面で支える能力が高いことを認め、2020年までに年1000億ドル(760億ポンド)の資金を動員することを約束した。
しかし、コペンハーゲン目標が遅ればせながら達成された2021年と2022年に関して、2万件を超える世界のプロジェクトを対象に行われた最新の報告分析では、多額の資金が産油国や世界第2位の経済大国である中国に流れていたことが明らかになった。
フランスやカナダと同程度の一人当たりGDPを有する化石燃料輸出国のUAEは、日本から気候資金として計上された10億ドル超の融資を受けた。案件には、アブダビ沖合の送電プロジェクト向けの6億2500万ドルや、ドバイの廃棄物焼却施設向けの4億5200万ドルなどが含まれている。
巨大な油田を抱え、サウジアラムコ(Aramco)の筆頭株主でもあるサウジアラビアは、世界の二酸化炭素排出国トップ10に入る。サウジアラビアは、日本からの融資として総額約3億2800万ドルを受け、そのうち2億5000万ドルは電力会社向け、7800万ドルは太陽光発電所向けであった。
自然資源防衛評議会(NRDC)で気候資金を担当するジョー・スウェイツ(Joe Thwaites)氏は、気候資金の全体的な流れは増加しているものの、最も貧しく脆弱なコミュニティに対しては依然として「十分な」規模では届いていないと指摘し、多重債務に苦しむ国々には、より多くの無償資金や譲許的条件の融資が必要だと述べた。
同氏はさらに、「これは慈善事業ではない。生活費の高騰、サプライチェーンの混乱、自然災害、強制移住、紛争など、私たちが日々目にする多くの危機の根本原因に対処するための戦略的な投資だ」と語った。
調査対象となった2年間で、ハイチ、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、イエメンなど、後発開発途上国に約330億ドルが約束された。一方、はるかに大きな額である約980億ドルが開発途上国全般に向けられた。この広いカテゴリには、インドのような下位中所得国や、中国のような上位中所得国も含まれる。さらに320億ドル相当の資金については分類ができなかった。報告期間中、インドは約140億ドルで最大の単独受益国となり、中国は主に多国間銀行から約30億ドルを受け取った。
分析によると、後発開発途上国の受け取り分が少ないのは、部分的にはそれらの国の人口規模が小さいことを反映しているが、同時に「開発途上国」というグループの構成そのものが、気候交渉における緊張の高まりの一因になっていることも示している。
例えば、中国経済は、国連が1990年代に中国を「開発途上国」と分類して以来、急速な成長を遂げており、一人当たり排出量はすでに欧州の水準を上回っている。中国は海外の気候関連プロジェクトに対する主要な資金供給国とみなされているものの、自国の拠出分を公式な国際枠組みで計上する動きには抵抗している。国連による開発カテゴリーは、1992年の創設以来見直されていない。
オーバーシーズ・ディベロップメント・インスティテュート(Overseas Development Institute)の気候プログラムディレクターであるサラ・コレンブランド(Sarah Colenbrander)氏は、「この状況によって、過去30年間で巨大なカーボンフットプリントを持つ豊かな国々となったイスラエル、韓国、カタール、シンガポール、UAEなどが、国際的な責任から逃れることを可能にしている。トーゴやトンガ、タンザニアのような国々と同じカテゴリーにこれらの国が残っていることは、はっきり言って不合理だ」と述べた。
世界で最も貧しい国々の中には、気候資金の3分の2以上を融資の形で受け取っているところもあり、多くの国がこうした借入条件や利払いに対応できないだろうと警告されている。
国際環境・開発研究所(IIED)で気候資金ディレクターを務めるリトゥ・バラドワジ(Ritu Bharadwaj)氏は、「気候資金の隠れた側面は、約束された金額の大きさではなく、その形態にある。気候資金は貧しい国々の財政負担を増やしている。たとえ譲許的な条件の融資であっても、多くの場合、それは受益国よりも貸し手側に有利な条件を含んでいる」と指摘する。
世界銀行のデータによれば、同じ期間に後発開発途上国が支払った対外債務の返済額は合計約913億ドルに上り、これはそれらの国々の気候資金予算の約3倍に相当する。過去10年間で、最貧国の対外債務返済額は3倍に増え、2012年の143億ドルから2022年には465億ドルとなった。
災害保護センターの金融専門家であるシャキーラ・ムスタファ(Shakira Mustapha)氏は、「従来の考え方では、成長を促す支出のために用いられるのであれば、より多くの債務を負うことは必ずしも悪いことではない。しかし、私が懸念しているのは、各国が古い借金を返済するためだけに新たな借金をしているのではないか、そして私たちは問題を先送りしているだけなのではないか、という点だ」と述べた。
日本のニュース通信社 Japan News Agency